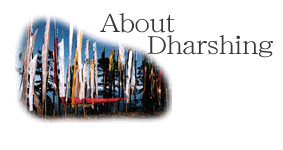|
◆人々の心を結ぶ祭
 四年ぶりのブータンは黄緑色にゆれるやなぎの芽ぶきと満開の桃の花で私達を出迎えてくれた。日本の陰暦と似たブータンの古い暦の二月、空港のある町、パロで開かれる春祭りツェチュにあわせての訪問である。五日間にわたって延々と繰り広げられる、舞踏と劇と歌、私達はそのほんのわずかの部分をかいまみたにすぎないが、その演技にこもる祈りは感じられた。 四年ぶりのブータンは黄緑色にゆれるやなぎの芽ぶきと満開の桃の花で私達を出迎えてくれた。日本の陰暦と似たブータンの古い暦の二月、空港のある町、パロで開かれる春祭りツェチュにあわせての訪問である。五日間にわたって延々と繰り広げられる、舞踏と劇と歌、私達はそのほんのわずかの部分をかいまみたにすぎないが、その演技にこもる祈りは感じられた。
この祭りの主要な舞踏は、十七世紀にブータンを統一したシャブドウン・ガワン・ナムゲルという高僧が密教の教えを伝えるためにつくりだしたものなので、踊り自体が祈りなのだ。国教がチベット密教のながれをくむ仏教なので、祭は人々の心を結ぶ。
◆これは踊る瞑想なのだろうか
祭の初日十九日、踊りは城と僧院をかねるゾンという巨大な建物の中庭でおこなわれた。笛と太鼓、どらの調べがお経のように単調だが、この世をこえた永遠を感じさせ、ずしりと心に響いてくる。音楽の中に、仏陀や菩薩をこの世によびよせる神秘の力がこもっていると信じられている。
私たちが祭の場に着いた時には、三つ目の出し物、有名な「黒帽の踊り」がはじまっていた。音楽にあわせてボン字の書かれた黒い帽子の踊り手が、くるくると旋回し跳躍する。骸骨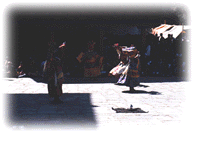 の彫り物の帽子飾りの下の赤、青、緑、黄、白の長いリボンが渦巻く。龍や波の模様の豪華な刺繍の長い衣装を身につけ、フェルトの長靴で地面をどらや太鼓にあわせて、力強くふみつける。魔除けの憤怒神を刺繍した前掛けがひらひらとゆれうごく。これはその土地に住む悪霊をなだめるためのもの。酒と米がまかれ、はじめは二拍子、その後四拍子となってえんえん一時間以上踊りつづけられた。 の彫り物の帽子飾りの下の赤、青、緑、黄、白の長いリボンが渦巻く。龍や波の模様の豪華な刺繍の長い衣装を身につけ、フェルトの長靴で地面をどらや太鼓にあわせて、力強くふみつける。魔除けの憤怒神を刺繍した前掛けがひらひらとゆれうごく。これはその土地に住む悪霊をなだめるためのもの。酒と米がまかれ、はじめは二拍子、その後四拍子となってえんえん一時間以上踊りつづけられた。
二十一人の黒帽たちは殺し、再生する力をもち、悪い霊魂を慈悲の怒りと知恵で追い払う。罪ある悪霊たちは無空のかなたへ消えさるのだ。踊り手の顔がだんだん恍惚感にあふれてくる。これは踊る瞑想だろうか。
彩り豊かな手織りの晴れ着をきて祭りの庭につどう人々、中庭をかこむ寺院の二階、三階に、あふれそうな人々の顔にも不思議な恍惚感は波のようにひろがっていく。これらの舞踏の力と祝福によって、すべての不幸は消滅し、幸福はいや増し、すべての願はかなえられると人々は信じている。
黒帽の踊り手たちは深く瞑想している神々の助けによって、インド舞踊の神秘的な手の動きムドラを演じ、地面を踏みしめる足の動きは神秘の幾何学模様、仏教の宇宙観であるマンダラを形づくるという。
◆延々とくりかえされる生と死
 緊張をほぐすようにアチャラとよばれる道化たちが滑稽なしぐさで観客を笑わせる。鼻の高い笑い顔の赤いお面をかぶり、背中と膝に白、黒、赤、緑、黄の四角形をたがいちがいに重ねてアップリケしてある赤い上着とズボンをはいている。ダムロという小さな鼓に似た太鼓と赤い陽根の形をした棒を持って、性的なしぐさや踊り手たちの物真似などをして、すべったり転んだり、そのたびに観客は陽気に笑いころげる。 緊張をほぐすようにアチャラとよばれる道化たちが滑稽なしぐさで観客を笑わせる。鼻の高い笑い顔の赤いお面をかぶり、背中と膝に白、黒、赤、緑、黄の四角形をたがいちがいに重ねてアップリケしてある赤い上着とズボンをはいている。ダムロという小さな鼓に似た太鼓と赤い陽根の形をした棒を持って、性的なしぐさや踊り手たちの物真似などをして、すべったり転んだり、そのたびに観客は陽気に笑いころげる。
アチャラは単なる道化ではなく、半神半人で未来を教えてくれる聖なる存在でもあるという。赤ん坊を抱いて清められた祭りの場をまわっているのは祝福を与えているのだろうか。アシュラとアチャ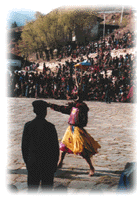 ラは同じルーツだろうか。 ラは同じルーツだろうか。
その後は黄色いスカートをはいて、動物の面をつけた踊り手たちによる、「ドラミツの太鼓の踊り」「八種類の霊魂の踊り」と続いた。これらの踊りは皆、踊り手に転生した神々によって踊られるといわれている。ねじのような旋回と高い跳躍、緊張の持続は、たしかに人間わざを超えているようだ。踊り手たちは僧院のわずかなバターランプの明りに照らされた、巨大な仏像のある部屋の静かな暗がりの中から、太陽の光りのふりそそぐ中庭に踊りだし、またその薄闇の部屋へもどっていく。死と生と生と死が延々とくりかえされる。僧院の内部の壁一杯に描かれた神々、骸骨の首飾りをつけた憤怒神や静かなやすらぎに満ちた菩薩などが人間の姿を借りてこの世に現われたような感じがする。
まだ踊りは続いていたが、パロのホテルは満員なので、車で一時間以上かかる首都ティンプーにもどらなければならなかった。後ろ髪ひかれる思いで、パロゾンを後にする。
◆リラックスした三日目
 翌日はティンプーの美術訓練学校や国立図書館、工芸センターなどを見てまわった。資料によると、今日のパロの祭りは会場をゾンの外の広場にうつし「死の王と王女の踊り」「民族舞踊」「太鼓をもった黒帽の踊り」「火葬場の王の踊り」「鹿と犬の踊り」などが演じられているはずだった。この次ぎには祭りに五日間ぴったりはりついて全てをこの目で見たい。そんな贅沢はこの国に住まないかぎり無理かもしれないが。 翌日はティンプーの美術訓練学校や国立図書館、工芸センターなどを見てまわった。資料によると、今日のパロの祭りは会場をゾンの外の広場にうつし「死の王と王女の踊り」「民族舞踊」「太鼓をもった黒帽の踊り」「火葬場の王の踊り」「鹿と犬の踊り」などが演じられているはずだった。この次ぎには祭りに五日間ぴったりはりついて全てをこの目で見たい。そんな贅沢はこの国に住まないかぎり無理かもしれないが。
三日目の二十一日、朝の九時ごろゾンの階段を緑の葉のついた柳の枝で編んだ冠をつけた男たち、キラという色あざやかな手織り布の晴れ着を着た少女たち、日本の着物に似たゴを着た青年たち、楽器を演奏する人々、僧侶、小坊主たちの行列がにぎやかに祭りのひろばにおりてくる。まるで縁日のように色々の店がならび、子供たちはかけまわる。みんな楽しそうに車座になってお弁当をひらいたり、おしゃべりしたり、儀式のような初日と違いみんなリラックスしている。
三人のアチャラが石畳の広場で兵士の訓練の即興劇をして、観衆をわかせている。一人が命令する側で、あとの二人はめちゃくちゃな兵隊。右を向けといえば左をむき、寝てしまったり、ひっくりかえったり、たわいもない演技だが、観客は笑うのがうれしいといったふうに笑いころげる。牛の交尾の真似をしたり、陽根型のこん棒を矢のようにあつかって弓を射る真似をしたり している。 している。
やなぎの葉の冠の長老たちの踊りのあと、「火葬場の王の踊り」がはじまった。四人の白い骸骨仮面をつけた踊り手が金属製のたて笛のボワーボワーという低い音と、チャチャラン、チャンという鉦の音にあわせて後ろにそったり前にかがんだり、旋回したりする。アチャラたちはわざとタイミングをはずして下手にそれを真似る。骸骨の爪は黒く長い。黄、赤、ピンク、緑、青のスカートがひるがえる。
これらの骸骨たちは、マンダラ宇宙の外端に住む神々で、仏法とその地域を守護し、教義を破る悪魔たちを無力化する。教義を畏敬するすべての生き物を守護し、より良い生まれ変わりのためにどうしたらよいかということを教えるのだという。
◆呑気で残酷でおかしな世界
いつまで続く単調な踊りに飽きて、露天をひやかしたり、祭りに来ている人々とおしゃべりしたり、町の食堂で昼食をとったりして、また、祭りの広場に着いたとき「憤怒神の踊り」「六種の聖飾をつけた英雄の踊り」はすでに終わってしまっていた。
「憤怒神の踊り」は憤怒神が悪霊を輪と箱の中に閉じ込め、主神儀式用の短剣で悪霊を殺す。この舞踊劇ではアチャラと男たちがまだ仏教に改宗していないものを演ずる。八世紀にブータンに仏教をもたらし、釈迦の生まれ変わりと信じられているグル・リンポチェが雷神に変身して、信じられないほどの恐怖を演じることで彼らを改宗させ、至福の天球に解放するという。
「六種の聖飾をつけた英雄の踊り」は五種類の骨の飾りを身につけ、手には太鼓を持った英雄の踊りで、太鼓の音に密教の神々が目覚め、輪廻の車にとらわれている感覚のあるものたちはこの踊りと音楽にみちびかれて輪廻から解放されるというのだ。骨の飾りはビーズ状になっていてスカートの上にうろこ模様につるされて、踊りと共に揺れる。見逃した踊りは特別面白そうだ。残念、残念。
 「高貴な男たちとその夫人たち」は劇仕立て。『昔、インドの北にあるナデムという王国に五百人のお后がいる王が住んでいた。ある日、猟師の息子が(生命の力)という名の蛇神を助け、そのお礼になんでももって帰れるなげなわをこの神から借りた。人間の娘とは比べものにならないくらいの美しい娘をつれて帰り、王にささげた。王はこの娘に夢中になり、相手にされなくなった五百人の王妃は、黒魔術師にこの娘を殺すように頼んだ。黒魔術師は王の父の夢にあらわれ、北の未開の国がこの国を侵略しようとしているから、急いで攻めて行き征服しないと、この国は破壊されるだろうと予言した。 「高貴な男たちとその夫人たち」は劇仕立て。『昔、インドの北にあるナデムという王国に五百人のお后がいる王が住んでいた。ある日、猟師の息子が(生命の力)という名の蛇神を助け、そのお礼になんでももって帰れるなげなわをこの神から借りた。人間の娘とは比べものにならないくらいの美しい娘をつれて帰り、王にささげた。王はこの娘に夢中になり、相手にされなくなった五百人の王妃は、黒魔術師にこの娘を殺すように頼んだ。黒魔術師は王の父の夢にあらわれ、北の未開の国がこの国を侵略しようとしているから、急いで攻めて行き征服しないと、この国は破壊されるだろうと予言した。
王は軍隊と共に北の国へ行くことになり、一緒に行きたいという娘の願いは、危険だからとしりぞけられ、娘は指輪と着物、髪にかぶっていた白い絹を王にわたして、人間の世界を去った。敵を征服した王は帰ると、内なる敵も滅ぼした。娘はふたたび人間界に帰り王と幸せに暮らした』というのがこの劇のもとになった昔話。
しかし、実際に演じられるのはもっとコミカルな話にかわっている。二人の王子が戦いに行き、二人の姫が残される。アチャラたちは姫にふざけかかり、さわぐ。世話をするように頼まれた老夫婦もつきころがされたり汚されたりする。王子が帰ると姫のスキャンダルを聞かされ、罰として姫の鼻を切ってしまう。よごれた老婆が近寄るとくさいので棒でおいはらう。その後、王子は姫と結婚し、罰として王子も鼻を切り、老婆も鼻を切られる。切った鼻を元に戻そうと医者がよばれるが、老婆がくさいので医者は棒でおいはらう。最後にみんな仲直り。姫は白い菩薩のような笑顔の仮面をつけて美しいキラを着てゆったりゆったりあるく。観衆は楽しそうにけちゃけちゃ笑いながら見ている。呑気で残酷でおかしな世界。
◆鹿と犬の踊り
最後は「鹿と犬の踊り」。もとになった話は『十一世紀、ミラレパという高僧がネパールとチベットの国境にある僧院の洞穴で深く瞑想していると、男の叫び声と犬の吠える声が聞こえる。すると赤い毛の鹿が身体中に汗をかき、おそろしさでふるえながら逃げてきた。ミラレパは憐れみをこめて宗教歌を歌うと、鹿は恐れを忘れミラレパの右膝によこたわった。そのとき鹿を追いかけて赤犬が光のように早く走ってきた。ミラレパは同じように宗教歌を歌って、はやる犬をしずめると犬はミラレパの左膝によこたわり、母と息子のように仲良く歌を聞いて いる。 いる。
犬の後を追ってきた猟師は恐ろしい顔をした強そうな男だった。「おまえは鹿と犬を守っている。自分も守れるかどうか見せてもらおうか」猟師は毒矢をミラレパにむけてはなった。弓の弦は切れ、矢は猟師のほうに向きをかえ、そして粉々になってしまう。ミラレパが歌を歌うと、茫然としていた猟師は心をいれかえ今までの悪業を告白し、二度と罪をおかさないという誓いをたて、修行して悟りを得た』というのだ。
実際の演技は二日目と三日目にわけて演じられる。最初の日は、二頭の犬と猟師、道化によるコミカルな劇である。猟にでかける前は僧をよんで儀式をしなければならないのだが、猟師と道化はふざけて、呼んだ僧も仏教の伝統に反した儀式をして観客の笑いをさそう。三日目はミラレパが長い白い衣に白いおだやかな表情の仮面をつけ白い帽子をかぶってあらわれる。手には巡礼の杖を持ち、右手は耳の近くにあてて、やわらかな声で歌う。鹿と犬と猟師が近くにくると、ミラレパは歌で彼らを改宗させる。改宗は犬と猟師がロープをジャンプして飛び越えることで象徴的に表現されるので、踊り手はアクロバットのような動きで観客をわかせていた。いつの間にか夕方の光りがミラレパの白い仮面を夕焼けの色に染めこの世ならぬ崇高さがただよっている。
◆伝説の寺院を詣でる
四日目はいままでの演目と重なる部分が多いので、パロから千メートルほど登った山の上にあるタクサン寺院にもうでることにした。タクサンというのは虎の巣という意味で、グル・リンポチェ(パドマ・サンババ)が八世紀、虎の背に乗ってこの国にチベットから密教を伝えたという伝説の寺院である。麓から見あげれば切りたった崖にへばりつくような寺院が小さくのぞまれる。ロバとポニーにのって急な坂道をのぼっていくと、そこここに桜草の花が咲いている。毒があるからロバもポニーも食べないそうだ。途中で出会ったまだ少女のおもかげのある尼僧はこれから六か月の修行をしにタクサン寺院に行くところだという。朝の三時から六時まで瞑想、朝食を食べて、八時から十一時まで瞑想、昼食をたべて一時から四時まで瞑想、夕食をたべて、五時から八時まで瞑想するのだという。瞑想のなかから少女はなにをつかむのだろうか。
たくさんの祈りのダルシンがヒマラヤンブルーの空にはためいている展望台でロバをおりると、岩にはりついているような四つの寺院が遠望された。一番高い山の上にあるのが、ザンドベリ、グル・リンポチェの幻想のなかでみた天国と同じ名前の寺、一番低いところにある寺がペーフーだという。観光客は特別の許可がなければ寺院までは入れず、ここから一時間ほど歩いて、ペーフー寺院がまじかに見えるところまで行ってもどってきた。真っ赤なしゃくなげ(エトメト)が咲き、さるおがせが風になびいている。
パロが標高二千メートルなのでここは三千メートルに近い。紫外線がつよく、風が止むととても暑い。高校生の陽気なガイド、ドジ(ドルジ)はフューフィフィッフィと口笛を吹いて風を呼ぶ。タイミングよく谷から風がふきあげる。この国では少年も魔法をつかうようだ。さるおがせを冠のように頭に巻き、ちいさカスタネットのような音を素手でひびかせて、祭りの踊りのふりで踊る。
◆心に鳴りつづける生への賛歌
 麓の村にドジの父の家があるので帰りに招待したいという。松の林をぬけると桃の花が咲きリンゴばたけにかこまれてドジの村が見えた。ゆるやかに川にむかう段丘がのどかにひらけて、白い壁に色とりどりの吉祥文様で飾られた柱が映える伝統的なブータンの農家が数軒、気持ちのいい間隔をおいて散在している。人とロバの歩けるほどの細い道が段々田んぼのあぜにそってつづき、道のそばを澄んだ小川が流れくだる。小川のそばで焚き火をして丸い石を焼いているのはドジの一番上の兄だという。小川から、長方形の木の箱に水がひかれ少女がそばに立っていた。石を三時間ほど焼いてこの木の箱にいれ、風呂に入るのだという。なんの囲いもなく本当に青天井の露天風呂。天国はあの高い山のうえの寺ザンドペリではなく、ここにあるんじゃないだろうか。 麓の村にドジの父の家があるので帰りに招待したいという。松の林をぬけると桃の花が咲きリンゴばたけにかこまれてドジの村が見えた。ゆるやかに川にむかう段丘がのどかにひらけて、白い壁に色とりどりの吉祥文様で飾られた柱が映える伝統的なブータンの農家が数軒、気持ちのいい間隔をおいて散在している。人とロバの歩けるほどの細い道が段々田んぼのあぜにそってつづき、道のそばを澄んだ小川が流れくだる。小川のそばで焚き火をして丸い石を焼いているのはドジの一番上の兄だという。小川から、長方形の木の箱に水がひかれ少女がそばに立っていた。石を三時間ほど焼いてこの木の箱にいれ、風呂に入るのだという。なんの囲いもなく本当に青天井の露天風呂。天国はあの高い山のうえの寺ザンドペリではなく、ここにあるんじゃないだろうか。
ドジの家では仏間に通されて、バター茶とシンチャンというどぶろくをごちそうになった。丸いままの小麦を煎ったものとつぶしたとうもろこしがつまみだった。バター茶は二杯以上おかわりするのが礼儀で、二杯以上飲めばその家の友人としてみとめら れるのだという。飲めばそばから注いでくれるのだ。仏間は見事な色あざやかな彫刻と仏像で飾られ祭りのとき踊り手が持っていたようなおおきな太鼓が飾ってある。胴の部分には青と金で龍の模様が描いてある。毎朝この太鼓をたたいてお祈りするのだという。 れるのだという。飲めばそばから注いでくれるのだ。仏間は見事な色あざやかな彫刻と仏像で飾られ祭りのとき踊り手が持っていたようなおおきな太鼓が飾ってある。胴の部分には青と金で龍の模様が描いてある。毎朝この太鼓をたたいてお祈りするのだという。
一階は物置と家畜小屋、二階が居住空間で田の字型。上にぎぼし型のくりぬきのあるちいさな窓から外をみると、自分が家で窓が目のような錯覚におちいる不思議な家だ。おだやかな笑顔の家族たち、額から私達を見あげる、赤いほっぺの恥ずかしがりやの子供たち。このままここにいて、日本に帰るのをやめたくなってしまう。
名残をおしみながら帰り道を歩く。人ためにつくられた土の道を歩くことの心地良さを身体じゅうで味わっている。夕日が山の端に沈もうとしたとき、ドジが澄んだよく通る声で歌い始めた。
「陽が山の端に沈むとき、わたしの心も沈む。
山が私たちをへだてるように、夜が陽をかくす。
でも朝がくれば、また陽はのぼり
私は山をこえてあなたに会いにいく。
恋人よ川のようにならないでおくれ。
川は流れていき、二度と戻らない」
山を越え、野を越えていくのびやかな声、ゆるやかな旋律。夕日が日にやけたドジの顔を赤くそめた。沈む太陽はまた明日よみがえる。そう心から信じていられる世界、明日を肯定的にとらえられる世界、ブータン。それがこの国に私をひきつけている。仏教が国教であるブータンの人々がマニ車をまわしながらとなえる経文「オンマニペメフム」、その意味が「生きとし生けるものすべてが輪廻の輪から解放されますように」だということ知った今でも、ブータンの人々と同じように私の心に鳴りつづけるのは生への賛歌である。
◆大タンカ開帳
祭りの最終日、二十三日は縦二十七・三メートル、横三十メートルのタンカと呼ばれるアップリケの仏画が年に一度開帳される。午前二時半、まだ真っ暗なホテルを出発して祭りの広場に向かう。ドジは起きられないと困るので一睡もしなかった といいながから太い線香の束に火をつけ車の中を清める。三時、まだ暗いゾンの階段を音楽を先頭に、キラを着た娘たち、ゴを着た青年たちの行列のあとに、僧によって赤い布につつまれたタンカが運びだされた。タンカが飾られる大きな建物の前には祭壇がつくられ、小さなろうそくの明かりとバターランプの明かりがさざなみのように揺れている。たくさんのそなえ物が捧げられ、少女たちが合唱する。 といいながから太い線香の束に火をつけ車の中を清める。三時、まだ暗いゾンの階段を音楽を先頭に、キラを着た娘たち、ゴを着た青年たちの行列のあとに、僧によって赤い布につつまれたタンカが運びだされた。タンカが飾られる大きな建物の前には祭壇がつくられ、小さなろうそくの明かりとバターランプの明かりがさざなみのように揺れている。たくさんのそなえ物が捧げられ、少女たちが合唱する。
ドラの音を合図に綱が引き上げられ、のぼる太陽のようにゆるやかに仏像の姿があらわれた。御来迎といったようなおごそかな雰囲気。中央にグル・リンポチェ、両側に菩薩が立ち、回りには釈迦をはじめとする十人の諸尊、下端には赤不動、青不動が絹の布で色鮮やかにアップリケしてある。タンカが全部開かれた瞬間、雲にかくれていた月が一瞬顔を出し、またすぐに雲にかくれた。夜明けとともに開帳されると聞いていたが、あたりはまだ真っ暗でおおきな電気でライトアップされていた。これはきっと外国からの観光客のためのサービスなのだろうが、月明かりとろうそくやバターランプの光、かがり火の明かりに浮きあがったタンカが見たかった。そして夜明けの青いひかりのうつろいと太陽が出る瞬間の感動を味わいたかった。
文明に毒されて、自然のわずかな光ではものが見えなくなってしまった私たち、ブータンの人々は暗闇でもものが見える。まっくらな道ですれちがう人でも、ガイドは昼間と同じように見分けて話をしている。私たちが得たものと失ってしまったものはどちらが大きいのだろうか。私たちには見えない神や仏がこの国の人々には本当に見えるのかもしれない。
(了)
写真撮影はすべて山口広海/八千代
|

 四年ぶりのブータンは黄緑色にゆれるやなぎの芽ぶきと満開の桃の花で私達を出迎えてくれた。日本の陰暦と似たブータンの古い暦の二月、空港のある町、パロで開かれる春祭りツェチュにあわせての訪問である。五日間にわたって延々と繰り広げられる、舞踏と劇と歌、私達はそのほんのわずかの部分をかいまみたにすぎないが、その演技にこもる祈りは感じられた。
四年ぶりのブータンは黄緑色にゆれるやなぎの芽ぶきと満開の桃の花で私達を出迎えてくれた。日本の陰暦と似たブータンの古い暦の二月、空港のある町、パロで開かれる春祭りツェチュにあわせての訪問である。五日間にわたって延々と繰り広げられる、舞踏と劇と歌、私達はそのほんのわずかの部分をかいまみたにすぎないが、その演技にこもる祈りは感じられた。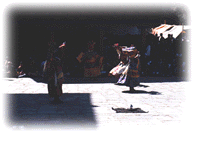 の彫り物の帽子飾りの下の赤、青、緑、黄、白の長いリボンが渦巻く。龍や波の模様の豪華な刺繍の長い衣装を身につけ、フェルトの長靴で地面をどらや太鼓にあわせて、力強くふみつける。魔除けの憤怒神を刺繍した前掛けがひらひらとゆれうごく。これはその土地に住む悪霊をなだめるためのもの。酒と米がまかれ、はじめは二拍子、その後四拍子となってえんえん一時間以上踊りつづけられた。
の彫り物の帽子飾りの下の赤、青、緑、黄、白の長いリボンが渦巻く。龍や波の模様の豪華な刺繍の長い衣装を身につけ、フェルトの長靴で地面をどらや太鼓にあわせて、力強くふみつける。魔除けの憤怒神を刺繍した前掛けがひらひらとゆれうごく。これはその土地に住む悪霊をなだめるためのもの。酒と米がまかれ、はじめは二拍子、その後四拍子となってえんえん一時間以上踊りつづけられた。 緊張をほぐすようにアチャラとよばれる道化たちが滑稽なしぐさで観客を笑わせる。鼻の高い笑い顔の赤いお面をかぶり、背中と膝に白、黒、赤、緑、黄の四角形をたがいちがいに重ねてアップリケしてある赤い上着とズボンをはいている。ダムロという小さな鼓に似た太鼓と赤い陽根の形をした棒を持って、性的なしぐさや踊り手たちの物真似などをして、すべったり転んだり、そのたびに観客は陽気に笑いころげる。
緊張をほぐすようにアチャラとよばれる道化たちが滑稽なしぐさで観客を笑わせる。鼻の高い笑い顔の赤いお面をかぶり、背中と膝に白、黒、赤、緑、黄の四角形をたがいちがいに重ねてアップリケしてある赤い上着とズボンをはいている。ダムロという小さな鼓に似た太鼓と赤い陽根の形をした棒を持って、性的なしぐさや踊り手たちの物真似などをして、すべったり転んだり、そのたびに観客は陽気に笑いころげる。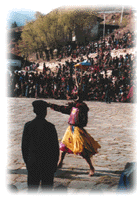 ラは同じルーツだろうか。
ラは同じルーツだろうか。 翌日はティンプーの美術訓練学校や国立図書館、工芸センターなどを見てまわった。資料によると、今日のパロの祭りは会場をゾンの外の広場にうつし「死の王と王女の踊り」「民族舞踊」「太鼓をもった黒帽の踊り」「火葬場の王の踊り」「鹿と犬の踊り」などが演じられているはずだった。この次ぎには祭りに五日間ぴったりはりついて全てをこの目で見たい。そんな贅沢はこの国に住まないかぎり無理かもしれないが。
翌日はティンプーの美術訓練学校や国立図書館、工芸センターなどを見てまわった。資料によると、今日のパロの祭りは会場をゾンの外の広場にうつし「死の王と王女の踊り」「民族舞踊」「太鼓をもった黒帽の踊り」「火葬場の王の踊り」「鹿と犬の踊り」などが演じられているはずだった。この次ぎには祭りに五日間ぴったりはりついて全てをこの目で見たい。そんな贅沢はこの国に住まないかぎり無理かもしれないが。 している。
している。 「高貴な男たちとその夫人たち」は劇仕立て。『昔、インドの北にあるナデムという王国に五百人のお后がいる王が住んでいた。ある日、猟師の息子が(生命の力)という名の蛇神を助け、そのお礼になんでももって帰れるなげなわをこの神から借りた。人間の娘とは比べものにならないくらいの美しい娘をつれて帰り、王にささげた。王はこの娘に夢中になり、相手にされなくなった五百人の王妃は、黒魔術師にこの娘を殺すように頼んだ。黒魔術師は王の父の夢にあらわれ、北の未開の国がこの国を侵略しようとしているから、急いで攻めて行き征服しないと、この国は破壊されるだろうと予言した。
「高貴な男たちとその夫人たち」は劇仕立て。『昔、インドの北にあるナデムという王国に五百人のお后がいる王が住んでいた。ある日、猟師の息子が(生命の力)という名の蛇神を助け、そのお礼になんでももって帰れるなげなわをこの神から借りた。人間の娘とは比べものにならないくらいの美しい娘をつれて帰り、王にささげた。王はこの娘に夢中になり、相手にされなくなった五百人の王妃は、黒魔術師にこの娘を殺すように頼んだ。黒魔術師は王の父の夢にあらわれ、北の未開の国がこの国を侵略しようとしているから、急いで攻めて行き征服しないと、この国は破壊されるだろうと予言した。 いる。
いる。 麓の村にドジの父の家があるので帰りに招待したいという。松の林をぬけると桃の花が咲きリンゴばたけにかこまれてドジの村が見えた。ゆるやかに川にむかう段丘がのどかにひらけて、白い壁に色とりどりの吉祥文様で飾られた柱が映える伝統的なブータンの農家が数軒、気持ちのいい間隔をおいて散在している。人とロバの歩けるほどの細い道が段々田んぼのあぜにそってつづき、道のそばを澄んだ小川が流れくだる。小川のそばで焚き火をして丸い石を焼いているのはドジの一番上の兄だという。小川から、長方形の木の箱に水がひかれ少女がそばに立っていた。石を三時間ほど焼いてこの木の箱にいれ、風呂に入るのだという。なんの囲いもなく本当に青天井の露天風呂。天国はあの高い山のうえの寺ザンドペリではなく、ここにあるんじゃないだろうか。
麓の村にドジの父の家があるので帰りに招待したいという。松の林をぬけると桃の花が咲きリンゴばたけにかこまれてドジの村が見えた。ゆるやかに川にむかう段丘がのどかにひらけて、白い壁に色とりどりの吉祥文様で飾られた柱が映える伝統的なブータンの農家が数軒、気持ちのいい間隔をおいて散在している。人とロバの歩けるほどの細い道が段々田んぼのあぜにそってつづき、道のそばを澄んだ小川が流れくだる。小川のそばで焚き火をして丸い石を焼いているのはドジの一番上の兄だという。小川から、長方形の木の箱に水がひかれ少女がそばに立っていた。石を三時間ほど焼いてこの木の箱にいれ、風呂に入るのだという。なんの囲いもなく本当に青天井の露天風呂。天国はあの高い山のうえの寺ザンドペリではなく、ここにあるんじゃないだろうか。 れるのだという。飲めばそばから注いでくれるのだ。仏間は見事な色あざやかな彫刻と仏像で飾られ祭りのとき踊り手が持っていたようなおおきな太鼓が飾ってある。胴の部分には青と金で龍の模様が描いてある。毎朝この太鼓をたたいてお祈りするのだという。
れるのだという。飲めばそばから注いでくれるのだ。仏間は見事な色あざやかな彫刻と仏像で飾られ祭りのとき踊り手が持っていたようなおおきな太鼓が飾ってある。胴の部分には青と金で龍の模様が描いてある。毎朝この太鼓をたたいてお祈りするのだという。 といいながから太い線香の束に火をつけ車の中を清める。三時、まだ暗いゾンの階段を音楽を先頭に、キラを着た娘たち、ゴを着た青年たちの行列のあとに、僧によって赤い布につつまれたタンカが運びだされた。タンカが飾られる大きな建物の前には祭壇がつくられ、小さなろうそくの明かりとバターランプの明かりがさざなみのように揺れている。たくさんのそなえ物が捧げられ、少女たちが合唱する。
といいながから太い線香の束に火をつけ車の中を清める。三時、まだ暗いゾンの階段を音楽を先頭に、キラを着た娘たち、ゴを着た青年たちの行列のあとに、僧によって赤い布につつまれたタンカが運びだされた。タンカが飾られる大きな建物の前には祭壇がつくられ、小さなろうそくの明かりとバターランプの明かりがさざなみのように揺れている。たくさんのそなえ物が捧げられ、少女たちが合唱する。